【一口コラム】 大型センサーを搭載した本格派GR
リコーから、正式にGRの発表がされました。発売は5月下旬で、直販価格は9万9,800円の見込みです。GRは、GR DIGITAL IVの後継機に当たりますが、イメージセンサーが1/1.7型からAPS-Cサイズに大型化されました。イメージセンサーのサイズを単純に比較すると約9倍となり、デジタル一眼レフに準じた描写性能を得たと言えます。
GRの主な特徴を挙げると、次の通りとなります。
- イメージセンサーは有効1620万画素APS-C型CMOSで、ローパスフィルターレスです。画素数的には、ニコン COOLPIX Aとほぼ同じとなります。
- 設定できるISO感度はISO100-25600です。GR DIGITAL IVはISO3200まででしたので、設定幅も3段分拡がっています。
- レンズは18.3mmF2.8(35mm換算で28mm相当)の広角単焦点です。GR DIGITAL IVは6mmF1.9(35mm換算で28mm相当)でした。なお、画像処理エンジンによる歪曲補正は行っていないとのことです。絞りは9枚羽根の円形絞りで、最短撮影距離はレンズ先端から10cm(GR
DIGITAL IVは1cm:どちらもマクロ時)となります。
- 4コマ/秒の連写性能、RAW時の連続撮影可能枚数は4枚。
- フルHD(30fps)での動画撮影に対応。
- 比較的コンパクトなボディ。外装はマグネシウム合金製。
- AF速度は約0.2秒。レンズ駆動方式、AFアルゴリズムの最適化、センサー読み出しの高速化によりGR DIGITAL IVを上回る撮影レスポンス。起動時間はAFモーターと沈胴モーターを別個に用意することで約1秒に短縮。
- 外付電子ビューファインダーには非対応なものの、オプションで光学ファインダーを用意。
GR(左側)とGR DIGITAL IV(右側)。ボディデザインは踏襲していますが、幅は8.4mm拡がっています。ボディ前面にあるマイクがステレオ化されています。
GR(左側)とGR DIGITAL IV(右側)。どちらも液晶モニターは3型123万ドットの高精細パネルです。親指部分にボタンが追加され、AF動作とシャッター動作を分離することも可能です。
GR(左側)とGR DIGITAL IV(右側)。ボディ上面のレイアウトはほぼ同じですが、モードダイヤルの項目が追加されています。APS-Cサイズのセンサーになったにもかかわらず、沈胴時のボディ厚は32.5mmから34.7mmへとわずか2.2mmの増に留まっています。
イメージセンサーとレンズの仕様が似ているニコン COOLPIX Aと比較したのが次の表です。
【リコー GRとニコン COOLPIX Aの比較】
| 機種名 |
GR |
COOLPIX A |
| イメージセンサー |
有効1620万画素
APS-C型CMOS |
有効1616万画素
APS-C型CMOS |
| レンズ |
18.3mm F2.8
(35mm換算:約28mm) |
18.5mm F2.8
(35mm換算:約28mm) |
| ファインダー |
- |
- |
| ISO感度 |
ISO100-25600 |
ISO100-6400
(拡張でISO25600まで) |
| シャッタースピード |
300-1/4000秒 |
30-1/2000秒 |
| 液晶モニター |
3型123万ドット |
3型92万ドット |
| 連写速度 |
4コマ/秒(RAWで4コマ) |
4コマ/秒(JPEGで26コマ、RAW+JPEGで9コマ) |
| 動画撮影 |
1920 X 1080(30fps) |
1920 X 1080(30fps) |
| 付加機能 |
ストロボ内蔵 |
ストロボ内蔵 |
| インターフェース |
USB、AV OUT、HDMI |
USB、HDMI mini |
| バッテリー |
290枚 |
230枚 |
サイズ
(W x H x D) |
117×61.0×34.7mm |
110×64.3×40.3mm |
| 重さ |
245g/215g |
299g/-g |
並べてみると、想定している撮影シーンは似ているように思います。幅はGRの方が広いですが、高さと厚さはCOOLPIX Aの方が大きくなります。。
GR(左側)とDP1 Merrill(右側)。両機種ともAPS-C型イメージセンサーと、35mm換算で約28mmの単焦点レンズを搭載しています。連写性能、動画性能もほぼ同等です。
GR(左側)とDP1 Merrill(右側)。液晶パネルはどちらも3型ですが、COOLPIX Aの92万ドットに対し、GRはRGBにWも加えた123万ドットのパネルが採用されています。インターフェースはCOOLPIX
Aの方がボタンが多いものの、ダイヤルはGRの方が使いやすそうです。また、スナップカメラとしては、オートフォーカスとシャッターボタンを分離できるGRの方が使い勝手が良いかもしれません。
GR(左側)とCOOLPIX A(右側:レンズは伸長状態)。ボディ本体の厚さはほとんど同じですが、沈胴時のレンズ厚に違いにより、仕様上の差が生じています。どちらもアクセサリーシューはレンズ光軸上に設けられています。
ニコンのCOOLPIX Aも魅力的な実力機でしたが、それに真っ向から立ち向かうようにGRが登場しました。定評のあるGRレンズを搭載しているだけに、実際の描写性能に期待が募ります。。
参考:リコーGR1(1996年10月発売、定価90,000円)。レンズは28mmF2.8。
GR1のサイズは117x61x34mmで175gでしたので、ほぼGRと同等です。なお、GR1はその後、GR1s、GR10、GR21、GR1vとラインアップが展開されました。
(2013年 4月17日 記)
|





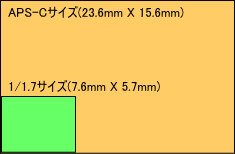
![]()